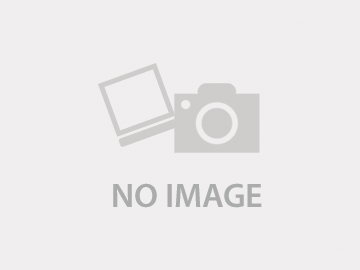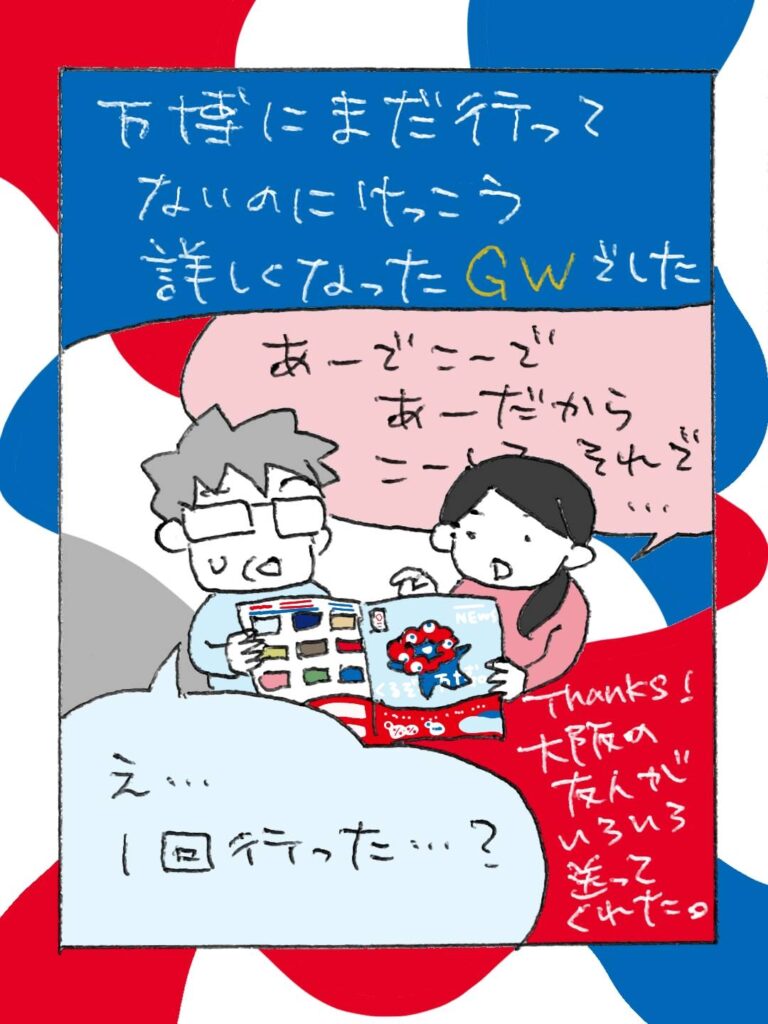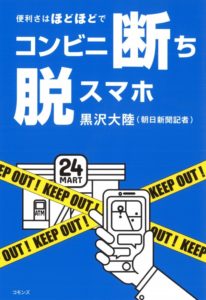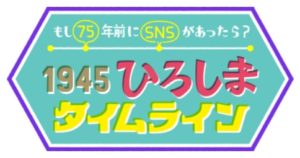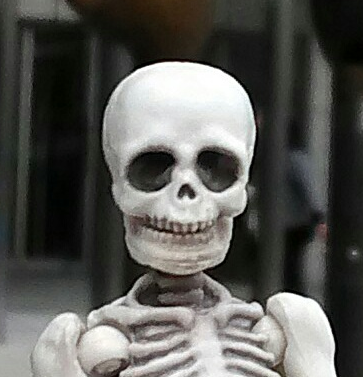↑書影からamazonに飛べます。
今回は、前から気になっていた水木しげる先生の『総員玉砕せよ!』です。
この記事の目次
いきなりですが、読後の感想。
むなしい……。
ものすごい虚無感に襲われました…。
あっという間にみんな死んじゃいます。
……。
どういう話なのか?
『総員玉砕せよ!』は、水木先生が自らの戦争体験をもとに描いた漫画です。
水木先生は兵隊として南方へ派遣され、マラリアに罹患し寝込んでいたときに空爆を受けて左腕を失うも、終戦を迎え日本へ帰国します。
この漫画の主人公は「丸山」という人物で、先生がモデルだろうから生き残るだろうと思って読むと―――裏切られます。
ラストの直前でかろうじて生き残り、敵の捕虜になるのかと思いきや…米兵に見つかり、「ジャップ」と言われ、ダーン(銃弾) です。
最後の独白も虚しさの塊でした。切な……
主人公の丸山は敵の銃弾にとどめを刺されますが、それまでに描かれる兵隊の日常でもどんどん死亡者が出ます。
物語は敵と交戦する前のキャンプ地の様子から。
キャンプ地を作るために土木作業をしたり、食べ物を調達するために魚を手りゅう弾で驚かせたり、上等兵から小言とびんたをもらったり、といった平時の様子をコミカルに描きつつ、デング熱、ワニ、盗み食い中に窒息、…と病気や不慮の事故での死にざまもたんたんと描かれます。
交戦する前に兵力どんどん失ってる!!?
いやホントそれなんですが、会敵してからはさらにどんどん兵力が失われ、応戦むなしく窮地に陥り、―――「玉砕命令」。
玉砕命令が出て生き延びてはいけない、捕虜(作中は「俘虜」と表記)になってもいけないという決まりがあったそうで、この玉砕命令が下ったにも関わらず、生き残った者には、自決強要。それに納得できず、上層部に掛け合おうとした軍医が無力感のうちに―――自決。
これって人間関係のごたごたでは…!?
戦争で兵隊が亡くなるとは、敵にやられて即死、もしくは傷病兵となり助からず…と思っていました。
それが、日常の事故だったり、誰が定めたのかわからない規律だったりで…? なんとも言葉が出てきません。
登場人物たちは、なんでこんな死に方をしなければならなかったのだろう。
終盤になるほど、「いのちだいじに!」という思いが強まるも、……先述のとおり、全滅します。
実際のところはどうだったのか
私が読んだ文庫本では、水木先生のあとがきが掲載されています。
それによると、この物語は「90%は事実」とのこと。
漫画は全滅で終わりますが、参謀(上の人)は上手に逃げ、実際は80人近く生き残ったそう。
この玉砕命令が出た島の後方にも味方がいて、同じ島で「あとで死ぬから、先に死ね」と言われても、なかなか死ねないと。たしかに。
また、物語を総員玉砕ではなく、1人生き残り、次の地点の連隊長に報告する別の展開も考えていたとも書かれています。
そして、物語を包み込む、虚しさや虚無感は、先生が感じられたことでもあったようです。
戦後、連隊長がこの玉砕について語ったことばを引用され、この言葉に対し、先生は「空しい」と書き添えていました。
連隊長は、この玉砕事件についてこういった。
「あの場所をなぜ、そうまでにして守らねばならなかったのか」
水木しげる『総員玉砕せよ!』あとがきより
玉砕。自決の強要。死にたい人がいて、その人が上の位にいて、大勢が巻き添えになった、という場合も多かったのかもしれません。
あとがきは2ページ強ですが、なかなか面白く、兵隊は消耗品であり、馬以下の生物とか、ひどいことも書かれています。
いのちより別の何かが大切だという声に抗えない環境の哀しさ。。。
最後に。
急に全然ちがう話のようなことを書きますが、2025年度前期(これを書いている今)のNHK連続テレビ小説は『あんぱん』
やなせたかし先生ご夫妻をモデルにしたドラマです。
晩年になってからやなせ先生は自らの戦争体験をエッセイにしており、その内容もドラマに反映されているとか。
やなせ先生のエッセイを読んだことがない私は、『あんぱん』を観ながら読んでみたくなったものの…
「今読んだら、ドラマのネタバレになるかも」
と思い至り、やなせ先生の著作は朝ドラが終わってから読むことにして、先に水木しげる先生の作品を読んでみました。漫画家つながりです。
(水木しげる先生ご夫妻も、朝ドラのモデルになってますね→『ゲゲゲの女房』)
朝ドラ『あんぱん』で描かれる、「逆転しない正義」が地球いっぱいに広まるといいなと思いながら、今回はここまでとします。